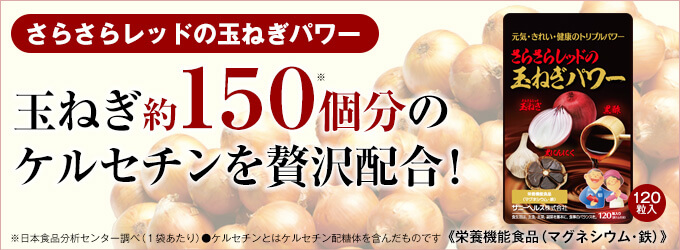ケルセチンの効果・効能とは?摂取できる食品と人気のケルセチンサプリを紹介!
玉ねぎやブロッコリー、リンゴなどに含まれるポリフェノールの一種であるケルセチン!
最近では、サプリメントなどにもよく配合されている注目の成分です。
それもそのはず!これらの嬉しい効果が期待できるからです。
- 血液サラサラ
- ダイエットサポート
- エイジングケア
- 生活習慣病を予防
- コレステロール値低減
ケルセチンの1日の摂取量の目安は100㎎~500㎎と言われていますが、これを野菜や果物から毎日摂取するのはなかなか大変です。
例えば、1日100㎎のケルセチンを摂るには、タマネギ1個を食べる必要があります。
毎日タマネギを何個も食べ続けるのは大変ですよね。
そんな方にオススメなのが、手軽にいつでもケルセチンを摂取できるサプリメントです。
ここでは、ケルセチンに期待できる効果・効能やケルセチンが配合された人気サプリメントをご紹介していきます。
目次
ケルセチンを摂取できる人気サプリメント
日清食品 DHA&EPA+ケルセチン
\日清食品が開発!海と大地のW成分で生活改善&サラサラ生活/

| 通常価格 |
5,500円(税抜) |
| 初回限定価格 |
1,980円(税抜) |
| 内容量 |
120粒(約30日分) |
今注目成分であるDHAとEPAにケルセチンをプラスしたサプリです。
ケルセチンはたまねぎに豊富なのですが、それは外皮の部分であるため摂取が難しいといわれています。
しかし、このサプリではたまねぎ2個分のケルセチンが配合されているので手軽にケルセチンを摂取することができます。
お馴染みの日清食品が開発したサプリなので安心して飲めるのでおすすめです!
>DHA&EPA+ケルセチンの詳細を見る
恵葉プレミアム
\生活習慣が気になる方やお酒好きの方が愛用/

| 通常価格 |
7,980円(税込) |
| 初回限定価格 |
- |
| 内容量 |
90粒(約30日分) |
恵葉プレミアムは、プリン体や糖・脂肪など健康診断で目を瞑りたくなるような結果が出てしまったという方におすすめです。
健康をサポートする希少な成分をバランス良く贅沢に配合しているので、イキイキした毎日を過ごすことができます。
口コミの評判も良く、実際に98%の方が満足しているそうです。
医療従事者が推奨するプリン体対策サプリでも、なんと堂々の1位を獲得するほどの注目サプリメントです!
>恵葉プレミアムの詳細を見る
ハウス タマネギの力
\ハウスが長年の研究で辿り着いたタマネギのWパワー/

| 通常価格 |
5,143円(税込) |
| 初回限定価格 |
2,572円(税込) |
| 内容量 |
90粒(約30日分) |
北海道産の生タマネギにわずか0.1%未満しか含まれていない希少成分・シクロアリインと玉ねぎの外皮に多く含まれるケルセチンを組み合わせたサプリメントです。
シクロアリインは流れをサポートする成分、ケルセチンはしなやかな毎日をサポートする成分とされています。
これらの成分に、ビタミンC・ビタミンE・ビタミンB6を配合している点が特徴です。
健康や食生活を気にしている方などにオススメされています。
>タマネギの力の詳細を見る
さらさらレッドの玉ねぎパワー
\マグネシウムや鉄も配合した栄養機能食品/
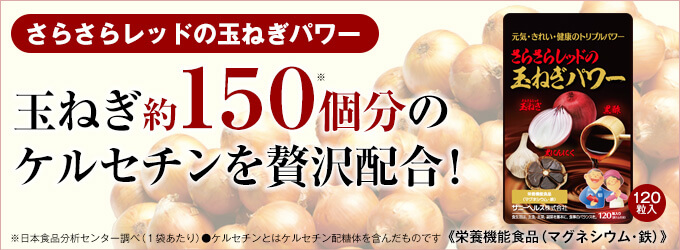
| 通常価格 |
3,800円(税込) |
| 初回限定価格 |
2,800円(税込) |
| 内容量 |
120粒(約30日分) |
血液循環を正常に保つマグネシウムを配合した栄養機能食品です。
あわせて、ポリフェノールをたっぷり含む黒ニンニク・必須アミノ酸やクエン酸を豊富に含む米黒酢・通常のタマネギに比べ1.5~3倍ものケルセチンを含む希少玉ねぎ・さらさらレッドなどを配合している点が特徴です。
1日分の目安に当たる4粒で96㎎のマグネシウム、2.04㎎の鉄、玉ねぎ5個分のケルセチンなどを摂ることができます。
10年後、20年後も、元気でしなやかな生活を送りたい方などにオススメされています。
>タマネギパワーの詳細を見る
オーガランド ケルセチン
\お手軽価格でサラサラ玉ねぎ習慣/

| 通常価格 |
640円(税込) |
| 初回限定価格 |
576(税込) |
| 内容量 |
30粒(約30日分) |
ケルセチンをたっぷり含むタマネギの外皮に注目したサプリメントです。
北海道産・兵庫県淡路島産のタマネギの濃縮エキスをたっぷり配合しています。
あわせて、ケルセチンの吸収を助ける亜麻仁油も配合しています。
亜麻仁油は、美容や健康に良いといわれる注目の油です。
1日の目安量にあたる1粒で玉ねぎ半個分のケルセチンを摂ることができます。
>オーガランドの詳細を見る
ケルセチンとは何か?
ケルセチンとは、野菜や果物などに含まれるポリフェノールのひとつです。
野菜や果物には、糖と結合したケルセチン配糖体という形で存在します。
ケルセチンそのものは脂溶性なので体内で吸収されにくいですが、糖と結合したケルセチン配糖体は水に溶けやすいので吸収されやすいとされています。
ケルセチンは黄色いポリフェノールです。
この特徴から、古くは染料として利用されていました。
最近では、健康にうれしい様々な効果・効能が注目を集め、サプリメントなどに幅広く利用されています。
ポリフェノールとは
ケルセチンが含まれるポリフェノールは、植物に含まれる色素成分です。
これまでに5000以上の種類が見つかっています。ポリフェノールは、植物が活性酸素などから身を守るため作り出す成分です。
ポリフェノールは、フラボノイド系とフェノール酸系に分かれます。
色素で出来たポリフェノールはフラボノイド、色素以外でできたポリフェノールはフェノール酸系に分類されます。
黄色い染料として使用されてきたケルセチンはフラボノイドに分類されます。
ケルセチンはビタミンP
ビタミンには含まれないもののビタミンとよく似た働きをするケルセチンは、ビタミン様物質のひとつに数えられます。
具体的には、ビタミンPに含まれます。
同じビタミンPとして、ルチン・ヘスペリジンが挙げられます。
ビタミンPには、ビタミンCを安定させる働き、ビタミンCの抗酸化作用をサポートする働きなどがあります。
これらの他にも様々な働きが期待できるとされています。
ケルセチンは魅力的な成分といえるでしょう。
ケルセチンの効果・効能は?

ケルセチンには、次の効果・効能などを期待できるといわれています。
血液をサラサラに
ケルセチンには、活性酸素から赤血球を守る働きがあるといわれています。
赤血球が活性酸素により傷つくと、柔軟性を失うため毛細血管など細い血管を通過しにくくなります。
ケルセチンは、赤血球を活性酸素から守ることで、その柔軟性を保ち血液の流れを保つ働きがあると考えられています。
この働きにより、血液をサラサラに保つといわれることがあります。
生活習慣病を予防
ケルセチンは、生活習慣病にもうれしい働きがあるといわれています。
例えば、血管に沈着したコレステロールが活性酸素に酸化されるのを防ぐことで動脈硬化を予防するといわれています。
動脈硬化は、高血圧・脳梗塞・心筋梗塞などのリスクを高める恐れがある生活習慣病です。
あるいは、インスリンの分泌を適切に保ち、血糖値を下げる働きなども期待されています。
血糖値の高い状態を糖尿病といいます。
自覚症状を現しにくい病気ですが、進行すると様々な合併症を引き起こし命にかかわります。
コレステロール値低減
以上のほかでは、コレステロール値を下げる働きも注目を集めています。
ケルセチンは、食事から摂ったコレステロールを小腸で吸収するときに働くタンパク質を阻害すると考えられています。
この働きにより、コレステロール値を下げる可能性があると考えられています。
抗酸化作用
ケルセチンの働きの多くは、優れた抗酸化作用によりもたらされます。
抗酸化作用とは、体内で過剰に発生した活性酸素を除去する働きです。
外敵から身体を守るためなどに働く活性酸素ですが、増えすぎると細胞や遺伝子にダメージを与えてしまいます。
ケルセチンには増えすぎた活性酸素を除去する働きがあると考えれているのです。
抗炎症作用
また、ケルセチンには抗炎症作用・抗アレルギー作用も期待できるといわれています。
ケルセチンには、炎症や腫れなどを引き起こすヒスタミンの分泌を抑える働きがあるからです。
この働きにより、アレルギー症状の軽減に役立つ可能性があるとされています。
ケルセチンでダイエット?!

ケルセチンはダイエットにも役立つ成分と考えられています。
なぜ、このように考えられるのでしょうか。
その理由を解説します。
ケルセチン配糖体が関係している
先ほど説明した通り、ケルセチンそのものは脂溶性なのでヒトの身体で吸収されにくい成分です。
しかし、糖と結びついてケルセチン配糖体になると水溶性が向上するので吸収されやすくなります。
ケルセチンとケルセチン配糖体では、吸収されやすさが違うことを覚えておきましょう。
血液サラサラによって痩せる?
ケルセチンがダイエットに役立つといわれる理由は、ケルセチンが脂肪分解酵素のリパーゼを活性化するからです。
リパーゼには、脂肪を脂肪酸とグリセロールに分解する働きがあります。
分解された脂肪の一部はTCA回路で燃やされます。
つまり、ケルセチンには脂肪の分解を助ける働きがあるのです。
この働きに着目したトクホ商品などが販売されています。
また、血液をサラサラに保つ働きによりダイエットを助ける可能性も指摘されています。
一部では、血液の巡りが悪いと代謝も悪くなり太りやすくなるといわれています。
この状態を予防することで、ダイエットを助けると考えられているのです。
いずれにせよ、ケルセチンはそのままではほとんど吸収されません。
糖と結びついたケルセチン配糖体を利用することが重要です。
肌も美しく!
ケルセチンは肌のエイジングケアにも活用したい成分といわれています。
優れた抗酸化力で活性酸素を除去すると考えられているからです。
活性酸素は、細胞の老化を引き起こす原因のひとつとされています。
ケルセチンは、美容を気にする女性にうれしい成分といえるかもしれません。
ケルセチンの摂り方

ケルセチンを活用したい方は、どのように摂取すればよいのでしょうか。
ケルセチンの摂り方を解説します。
1日の推奨量・摂取量
厚生労働省が発表してる「日本人の食事摂取基準(2015年版)」にケルセチンの推奨量・摂取量に関する記載はありません。
一般的な摂取量の目安といわれているのが1日あたり100㎎~500㎎です。
何かしらの目的をもってケルセチンを摂りたい方は、この量を参考にするとよいかもしれません。
摂取のタイミングは?
摂取のタイミングに関しても特別な指定はありません。
食事から摂りたい方は食事のタイミングで、サプリメントなどから摂りたい方は都合の良いタイミングで摂ればよいでしょう。
1度にまとめて摂るより、複数回に分けて摂った方が体に吸収されやすくなります。
また、ある程度の期間は継続して摂ることも重要です。
妊婦さんには付加量が必要?
妊婦さん・授乳婦さんに関する付加量についても特別な指定はありません。
現在のところ、安全性に関して十分なデータは集まっていないとされています。
リスクを避けるため、妊婦さん・授乳婦さんは、ケルセチンをサプリメントなどから摂ることは控えたほうが良いと考えられています。
ケルセチンの注意点や副作用
ケルセチンを摂りたい方は、注意点なども抑えておきましょう。
過剰摂取と欠乏の影響を紹介します。
過剰摂取すると?
食品に含まれる成分なので、基本的には安全に利用できると考えられています。
食事などから摂る場合は、過剰摂取のリスクはほとんどありません。
サプリメントなどを利用する方は、過剰摂取に気をつけましょう。
ケルセチンを摂りすぎると、頭痛や手足のしびれなどが現れることがあります。
これらが現れた方は病院で相談しましょう。
欠乏すると?
一部では、ケルセチンが欠乏するとアレルギーの症状が出やすくなる、あるいはアレルギーの症状が強くなるといわれています。
気になる方は、ケルセチンが欠乏しないように気をつけるとよいかもしれません。
ケルセチンと相性の良い成分とあまり良くないものとは?
ケルセチンを活用したい方は、相性の良い成分と相性のあまり良くないものも抑えておきましょう。
ケルセチンを効率よく利用できるはずです。
相性が良い成分
ビタミンC
ビタミンPのひとつとされるケルセチンは、ビタミンCの働きをサポートします。
具体的には、ビタミンCを安定させる働き、ビタミンCの抗酸化作用を支える働きなどが期待できます。
これらの働きが気になる方は、ケルセチンとビタミンCを一緒に摂ると良いでしょう。
ビタミンCは、ブロッコリーやパプリカ、レモンなどに含まれています。
相性がいいもの
油
ケルセチンは脂溶性の成分なので、油と一緒に摂ると吸収率がアップします。
植物油や肉類、青背魚類などと一緒に摂るとよいかもしれません。
摂り方に悩む方には油炒めがおすすめです。
ケルセチンを豊富に含むタマネギなどを植物油で炒めてみてはいかがでしょうか。
相性があまり良くないもの
医薬品
免疫抑制剤の代謝を阻害する可能性、抗生物質の作用を阻害する可能性などが指摘されています。
何かしらの医薬品を服用している方は、念のため主治医に相談したほうがよいかもしれません。
ケルセチンを多く含んでいる食品

ケルセチンは毎日の食事から摂ることができます。
どのような食品を利用すればよいのでしょうか。
玉ねぎ
ケルセチンを含む身近な食品の代表です。
100gあたり28~50㎎程度のケルセチンを含みます。
100gは中サイズのタマネギ2分の1個程度です。
様々な料理に利用できるので、上手に活用すればしっかりケルセチンを摂ることができます。
アスパラガス
タマネギのほかでは、アスパラガスもケルセチンを豊富に含みます。
100gあたりの含有量は22㎎程度です。
玉ねぎに比べると含有量・用途とも少ないですが、ケルセチンをたっぷり含む貴重な食品といえるでしょう。
レタス
身近なところでは、レタスにもケルセチンは含まれています。
ただし、含有量はそこまで多くありません。
しかし、サラダなどで手軽に摂れるので、レタスもケルセチンを摂りやすい食品といえます。
ブロッコリー
以上のほかではブロッコリーもケルセチンを含みます。
含有量はそれほど多くありませんが、ケルセチン配糖体の形で含まれているので吸収されやすい点がポイントです。
ブロッコリーもケルセチンを摂りたい方が活用したい食品です。
リンゴ
100gあたり4㎎程度のケルセチンを含みます。
デザートなどで利用しやすい点が魅力です。
食事だけではケルセチンの摂取量に限界があると感じる方はリンゴを利用するとよいかもしれません。
まとめ
ケルセチンは、野菜や果物などに含まれるポリフェノールの一種です。
具体的には、フラボノイドに分類されます。
その働きからビタミン様物質、ビタミンPと呼ばれることがあります。
これらが気になる方は利用すると良いでしょう。
何かしらの目的をもって摂取したい方には、サプリメントの利用がオススメです。
サプリメントであれば、確実かつ手軽にケルセチンを摂ることができます。
ケルセチンが気になる方は、毎日利用しやすいサプリメントを探してみてはいかがでしょうか。
- ホーム
- 健康食品
- ケルセチンの効果・効能とは?摂取できる食品と人気のケルセチンサプリを紹介!